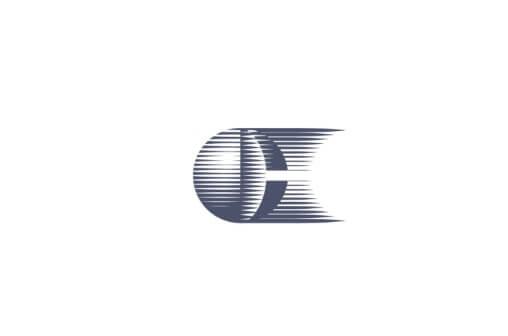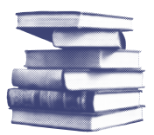
小説は、社会を映す鏡といわれます。二〇世紀までは、人の内面や裏側を描き出していましたが、二十一世紀の前後から、現代社会の問題や近未来社会の状況をフィクションで表現するようになりました。小説という鏡に映された「像」を分析することを通して、現代あるいは近未来の「社会」の問題や状況が鮮明にとらえられると考えられます。これまでの小説の読み方とは異なった、探究的な読み(分析と考察)によって、近未来を見通す文学探究力を伸ばしてみませんか。


近未来探究文学ゼミナールの活動ターム
-
ガイダンス
文学から未来を予測するとは? -
人間とその周囲との関係を考える
-
新しい家族・社会を考える
-
今までの考察を元にして
各自研究発表

- 学術顧問:
植山 俊宏 先生の略歴 - 2003年4月から京都教育大学国文学科教授。
2017年から2023年まで全国大学国語教育学会常任理事。2021年から2023年まで京都教育大学副学長。2023年から全国大学国語教育学会理事長。著書『リーダーシップとしての「指導言」-高校文学探究学習の指導において-』「読み」の授業研究会 2023、 『新たな学びを創る』中学校・高等学校国語科教育研究 全国大学国語教育学会 2019、『国語科と生涯学習』全国大学国語教育学会 2019など多数。

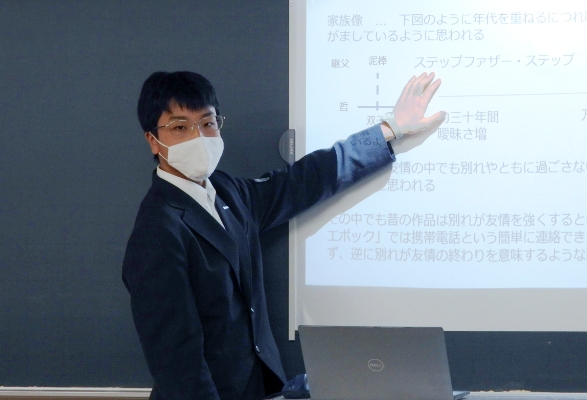


教員の声
文学なんて役に立たないと
思っているあなたに。
国語科 久世 貴章 先生
近未来探究文学ゼミは一言で説明すれば「刺激的な講座」です。
皆さんは小説を読むと聞いてまず何を思い浮かべますか?読んだあとに感動する、主人公や登場人物に共感する。もちろんそういった読み方も小説の楽しみ方のひとつですけれども、ここで小説と呼ばれるものをもう一回見直してみましょう。
小説を創作するのは当然作者です。そこには作者が見た世界が投影されています。文学ゼミはそこに注目します。たとえば三十年前の小説で描かれた友情と、十年前の友情、そして今の友情は、全て同じでしょうか?違うのですね、これが。
面白いことに同じテーマでも、時代ごとに視点が違うんですね。その当時はあたりまえだったことも後から振り返れば違和感や不思議な所が見えてくる。そのズレから未来をも見通せるかもしれない。
言葉を使った作家の想像力はたくさんの可能性を秘めています。近未来探究文学ゼミが刺激的なのは、そんな未来を見通す力を皆さんが身に付けることができるからなのです。